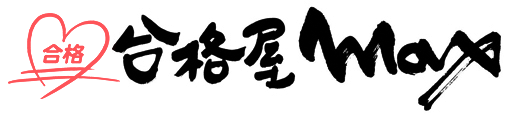テスト対策が始まる!
中総体後、今期、初めてのテスト対策が始まります。初めての方もいらしゃるので、テスト対策ついてご説明します。初めてではない方も、改めて確認して下さい。お願いします。
テスト前2週間は特別時間割に変わります。普段の時間割と異なりますのでご確認下さい。この間、回数は増えますが、授業料は変わりません。
例えば、週2回コースの場合だと、年間授業回数は、12ヶ月×4週×2回=96回に、夏冬春の各8回の24回を加えて120回の授業があります。<120回以外に、回数にカウントしてしていない分は、サービスです。昨年は、サービス分が年間で30回を超えました。毎回の延長分などはカウントに入れていません。>
この120回の授業をテスト前に集中して多く分配しています。そのために、週2回コースの方でも、テスト前は、回数が多くなります。いつの分が、どこで行われたかを明確にするために、配布している時間割には「5月⑦」という具合に、その授業が何月分の何回目の授業にあたるのかを明示しています。
ですから、例えば「5月⑦」が6月3日になっているとか、逆に「10月④」が9月18日になったりとか、カレンダーとの間にずれが生じます。
また、このテスト対策期間中のは、学年によっては、ほぼ毎日になりますので、この間の欠席は、物理的な問題で不可能です。ただし、① 正規では80分が1コマ授業ですが、この間は1回がそれ以上の時間でも、1コマと数えています。② 120回の枠に入らない分は「サービス」と表示してあります。この2点でお許し下さい。
通常は、テスト前2週間からテスト対策に入ります。6月の中間テストだけは、中総体とテストの間が2週間未満の学校の場合は、2週間とれないことがあります。振替休日を利用して、回数は確保しています。
100点ドリルで成績を上げる。
期間中は、解説だけでなく演習も教室内で行います。名物の100点ドリルです。一度間違えた問題・当然できないといけないテストに出る問題(指定問題)を2回連続して100点になるまで繰り返します。
テスト対策期間中の、家でやってきた分も提出したものは、カウントに入れて扱います。不正なくやってください。
100点ドリルを始めると、「そんなことしたら覚えちゃう」と言う子がいたりします。「???」です。 覚えるためにやっています、覚えて下さい。<今まで、勉強って何だと思っていたのかしら?>
初めての子の場合
特に今まで、本当に何もしてこなかった子ですと、かなり負担に感じてしまう場合があります。やる前に、時間割を見て、量に圧倒されて、参ってしまうケースでは、量を調整します。
特に今回が初めてであれば、「やればできる」ことを手ごたえとして感じてもらうことが一番大切なことです。そう感じることができれば、次回はもっともっと意欲的になれます。それを引き出すための布石を打っていきます。お子さんの様子を見て、無理だなと思う場合は連絡をください。また、こちらの方からご連絡するケースもございます。
学校からの課題は、基本、家でやってほしいと考えています。テスト対策が始まる前までに、終了しておくことがベストです。まったく何もしていない子も、まま見受けれらますので、一通りのテスト対策が終わったら、学校の課題をやる時間を取ることもあります。特にその課題の中から、テストに問題が出る場合はやる価値はあります。ただ、やればいいだけ、出せばいいだけ(失礼)の課題に、塾での時間を割きたくないのが本音です。
できる子の感覚
「こんなに勉強したのは初めて」とよく聞きます。だから、ほとんどの子がいい結果を取ることができます。
しかし、中には、どのぐらいでしょうか。15人に1名ぐらいの感じだと思いますが、空回りしたり、バランスをくずしたりして、「アレ?」って場合があります(2回連続しては起こったことがありません)。
そんな場合でも、テストを受けている時、いつもよりできる、やった問題がたくさんあった、「あ~ 取れそう」などの手ごたえは得ています。そういう感覚を大事にしてあげてください。
どのぐらいやれば、わかるのかって感覚です。ある程度、勉強しないと出てこない感覚です。さらに言えば、この感覚の有無が、できる子とそうでない子の大きな違いの一つです。
例えば、普段の仕事で、この量ならこれぐらいの時間がかかるという感覚がありますよね。ところが、新人にはそれがありません。食事の準備も同じだと思います。今日の献立であれば何分あればできるという感覚です。成績のいい子には、この感覚があります。この内容なら、自分なら大体何分で終わる。
もっと勉強に慣れた子だと、「テスト対策中に、何点分の勉強終わった」と聞くと、「だいたい60点分ぐらい。あとは●●をやれば80~90点になります」と言う会話ができます。今度のテスト前に、子どもに、「今、何点分の勉強が終わったの」と聞いてみてください。 子どもに感覚のあるなしがカンタンにわかります。感覚がまったくない子だと、何でそんなことわかるの?って怪訝な顔をします。
こういう子の場合、たとえ今回、点がよくても安心できません。自分がどのぐらいやると、その結果、どうなるのかの感覚がまだないので、まだしばらくは、上がった、また下がったを繰り返すことになります。それは、仕事に慣れない新人と同じで、やってみないとその結果はわからないのです。
食事の準備をするのに、そんなことってありませんよね。やる前に、だいたいこうなると予想がつけられます。同じように、勉強になれている子の「このままじゃヤバイ」はあてになります。しかし勉強に慣れてない子の「まあ、だいたい」はあてになりません。
テスト対策で、なぜこんなに時間を使うのか。
それは、普通の中学生だと、教室で時間を取れば、意外なほど頑張れるのに、自分ひとりではできないからです。
口では一人前のことを言うようになりましたが、精神的にはまだ幼いからなのか、一人で勉強するつらさに耐えられないのです。そこには、それなりのトレーニングが必要です。小4.5ぐらいから鍛えてきた子が、ようやく一人で、できるようになるのが、中2.3年生の時期です。
家で、「勉強しろ」と言ったとします。まず、子どもに、その気持ちがあったとしても、なんかカチンときています。ムカついています。そして、子どもを無理やり勉強部屋に行かせて、その後、テレビでも見ていると、子どもの方は「何で自分だけ」と感じて、イライラしているか、暗い気持ちになっているかです。
部屋には行ったものの、勉強は手についていません。だからと言って、子どもの勉強に付き合って、家族全員でテレビを消して「勉強の時間」っていうのもなかなか大変です。 中学生ぐらいの子たちは、口では一人前のことを言えるようになりましたが、本当に、自分のために頑張るということが、意外や意外、うまくできないんです。
<そこが、中学生の難しい所> ところが、誰かが一緒に付き合ってくれると、結構 頑張れるんです。だから、もう少し大人になるまで、自分で自分のために頑張れるようになるまで 付き合おうというわけです。子どもが将来、○○○になりたいと思った時に、もうその可能性はほとんどないという事態だけにはなってほしくないのです。
何を希望するかは子どもに任せるけど、親として選択の自由がある状態にはしておきたい。「厳しい」とか「長い」とか、子ども達からも嫌われることもありますが、その子どもたちが、「楽しかった」「おもしろかった」「勉強が好きになった」「自分に自信がもてた」「人間的にも成長させてくれた」と評価してくれています。
そして、この過去5年間で途中で辞めた子は数名です。この数字は、何だかんだ言っても、子どもから信頼してもらえている証と信じて、今回もテスト対策に望みます。
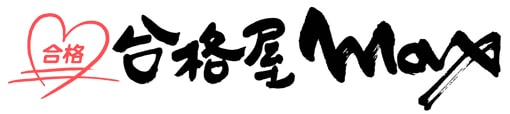
◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998 989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1
◆幸 町 教室 ☎295-3303 983-0836 宮城野区幸町3-4-19
電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30